記事の最後ってどうまとめたら良い?
まとめ方のポイントってあるの?
まとめってそもそも必要なの?
このようにお悩みではないでしょうか。
これから記事制作を検討している方は、ぜひ参考にしてください。

1000社以上のSEO記事を作成。
SEO対策のことならなんでもご相談ください!
これから記事代行の外注を検討されている方は、記事制作代行NEOへご相談ください。記事制作代行NEOでは、業界最安水準の文字単価3円〜にて制作を行っております。
どの業者よりもリーズナブルかつ高品質な記事制作を行わせていただきます。キーワードの選定・執筆・ワードプレス入稿・リライト・SEO対策まで一括してご依頼いただけます。
まずはお気軽に以下のリンクよりご相談ください!
記事の「まとめ」とは何か?基本を押さえよう
そもそも、記事の「まとめ」とはどのような役割を持っているのでしょうか。
ここでは、まとめの概要や本文との違いを解説します。
まとめ部分の役割と目的
記事の「まとめ」は、本文全体の要点や結論を簡潔に整理し、読者の理解を深める重要なパートです。読み終えた読者に内容を再確認させることで、記憶に残りやすくなります。また、記事全体の論理構成を補強し、読後感を良くする効果もあります。
特に情報量が多い記事では、要点を絞って提示することで読者の満足度が高まり、離脱を防げる点が大きなメリットです。さらに、次の行動を促す「行動喚起(CTA)」を添えることで、商品の購入や他記事への誘導など、マーケティング効果を高める役割も果たします。
本文とどう違う?記事構成における位置づけ
本文はテーマに沿って情報を展開し、主張・根拠・具体例などを段階的に解説するパートです。一方、「まとめ」はその本文を振り返り、要点を再提示して読者の理解を整理する位置づけにあります。
本文では新しい情報を順序立てて提示するのに対し、まとめは情報の取捨選択を行い、読者に印象づけたいポイントだけを絞って示すのが役割です。また、記事全体の締めくくりとして読後の納得感や行動喚起(CTA)につなげる点で、構成上も非常に重要です。
記事のまとめが重要な理由とは?
ここでは、記事のまとめが重要な理由を詳しく解説します。
読者に本文の内容を分かりやすく伝えるため
記事のまとめは、読者が本文の内容を整理しやすくするために重要な役割を持ちます。特に、情報量の多い記事では、すべてを理解するのが難しく、読者が途中で離脱してしまうことも少なくありません。
しかし、最後に要点を簡潔にまとめることで、本文を読まなくても重要なポイントを押さえることができます。また、「結局この記事で伝えたかったことは何か?」を明確にすることで、読者の満足度も高まり、記事の印象を強く残すことが可能です。
読者の購買意欲を高めるため
記事のまとめ部分は、読者の購買意欲を高める重要なポイントになります。例えば、商品レビューや比較記事では、本文で紹介した商品の特徴やメリットを整理し、最後に「この商品は○○な人におすすめ」とまとめることで、読者が購入を決断しやすくなります。
また、記事全体を読んだ読者に対し、「この商品を買うとどんなメリットがあるのか」を強調することで、購買につながる可能性が高まるでしょう。特に、限定キャンペーンやお得な情報を最後に入れると、購買意欲をさらに刺激できます。
記事のまとめ方によって製品やサービスが売れるか変化する
まとめの書き方一つで、製品やサービスの売れ行きが変わることもあります。単に情報を整理するだけでなく、「この商品を使うことでどんなメリットがあるのか」「購入しないことでどんなデメリットがあるのか」など、読者の心理に訴えかけるまとめ方を工夫することが重要です。
例えば、「この商品は人気があり、在庫が少なくなってきています」と書くだけで、読者に「今すぐ購入しなければ」という気持ちを抱かせることができます。記事の目的に応じて、最適なまとめ方を選ぶことが売上向上につながるでしょう。
まとめから別記事に誘導することもできる
記事のまとめ部分は、読者を別の記事へ誘導する役割も果たします。例えば、商品レビュー記事の最後に「この商品の詳しい使い方はこちら」と関連ページのリンクを貼ることで、読者の回遊率を高めることが可能です。
特に、SEOを意識する場合、内部リンクを適切に配置することで、サイト全体の評価を向上させる効果も期待できます。また、読者が興味を持ちやすい情報を提供し続けることで、サイトの滞在時間を延ばし、コンバージョン率の向上にもつながります。
読者の読み飛ばしを防ぐことができる
多くの読者は、記事を流し読みする傾向があり、重要なポイントを見落とすことが多いです。しかし、記事の最後にまとめを用意しておくことで、本文をしっかり読まなかった読者でも、記事のポイントを理解しやすくなります。
特に、リスト形式や箇条書きを活用すると、視覚的にもわかりやすくなり、記憶に残りやすくなるのが特徴です。また、まとめ部分で「この記事で紹介した○○は~」と本文の要点を補足することで、読者が再度本文を読み直すきっかけを作ることができます。
これから記事代行の外注を検討されている方は、記事制作代行NEOへご相談ください。記事制作代行NEOでは、業界最安水準の文字単価3円〜にて制作を行っております。
どの業者よりもリーズナブルかつ高品質な記事制作を行わせていただきます。キーワードの選定・執筆・ワードプレス入稿・リライト・SEO対策まで一括してご依頼いただけます。
まずはお気軽に以下のリンクよりご相談ください!
記事のまとめの書き方は?
ここでは、効果的なまとめの書き方について解説します。
本文の内容を分かりやすくまとめる(箇条書きなども使う)
記事のまとめでは、本文の要点を簡潔に整理し、読者が短時間で内容を理解できるようにすることが重要です。特に、箇条書きを活用することで、視覚的に見やすく、要点を把握しやすくなります。
記事制作社独自の視点での意見や考察を書く
ただ本文を要約するだけでなく、記事制作側の視点を加えることで、読者に新たな視点を提供できます。特に、製品やサービスのレビュー記事では、メリットだけでなくデメリットも正直に書くことで、信頼性が向上するでしょう。
このように独自の見解を加えることで、読者が納得しやすくなり、購買意欲の向上につながります。
読者に対して製品やサービスの訴求を行う
まとめ部分では、本文で紹介した製品やサービスを読者に効果的に訴求することが重要です。特に、「この商品を使うことでどのようなメリットがあるのか?」を明確に伝えると、購入や申し込みにつながりやすくなります。
このように具体的なメリットやキャンペーン情報を記載すると、読者の購買意欲を高めることができるでしょう。
適度に改行を入れる
文章が詰まりすぎていると、読者は内容を理解しづらくなり、途中で離脱してしまう可能性があります。適度に改行を入れることで、視認性を向上させ、読みやすい記事に仕上げることが可能です。
特にスマホで記事を読む読者が多いため、改行を意識することで、ストレスなく読んでもらうことができます。
CTAを設置する
CTA(Call To Action)は、読者に次の行動を促す要素で、記事のまとめに設置することで、コンバージョン率を向上させられます。具体的には、「購入ボタン」「資料請求リンク」「問い合わせフォーム」などを設置するのが効果的です。
また、CTAを目立たせるために、ボタンのデザインを工夫したり、読者が行動しやすい表現を使うことも重要となります。
検索キーワードを盛り込んだまとめにする
SEOを意識するなら、まとめ部分にも検索キーワードを自然に盛り込むことが重要です。特に、記事のターゲットキーワードを使いながら、ユーザーの疑問に答える形でまとめると、検索順位の向上につながります。
このように、キーワードを盛り込みつつ、自然な文章でまとめることで、検索エンジンにも評価されやすくなります。
これから記事代行の外注を検討されている方は、記事制作代行NEOへご相談ください。記事制作代行NEOでは、業界最安水準の文字単価3円〜にて制作を行っております。
どの業者よりもリーズナブルかつ高品質な記事制作を行わせていただきます。キーワードの選定・執筆・ワードプレス入稿・リライト・SEO対策まで一括してご依頼いただけます。
まずはお気軽に以下のリンクよりご相談ください!
記事のまとめを書く際の注意点は?
ここでは、記事のまとめを書く際に気を付けるべきポイントを解説します。
長すぎず短すぎない文章にする
まとめ部分の文章は、簡潔でありながら要点を押さえることが重要です。短すぎると読者に伝わりにくく、逆に長すぎると本文と変わらなくなり、読者が飽きてしまいます。
理想的な長さは200~300文字程度。記事の要点を端的に整理しつつ、読者が理解しやすいように工夫しましょう。例えば、箇条書きを活用して要点を整理すると、読みやすさが向上します。
また、文章のリズムを意識し、冗長な表現を避けることで、最後までスムーズに読んでもらえます。
無理にSEOキーワードを盛り込みすぎないようにする
SEOを意識することは大切ですが、まとめ部分にキーワードを詰め込みすぎると、不自然な文章になり、読者の離脱を招く原因になるでしょう。Googleの検索アルゴリズムも、キーワードの不自然な詰め込みを評価しないため、むしろSEO効果が下がる可能性もあります。
まとめでは、あくまで自然な流れの中でキーワードを取り入れることが大切です。例えば、「POSレジを導入することで業務効率が向上し、売上管理も簡単になります」といった形で、情報を自然に盛り込みましょう。
強引に製品やサービスを紹介しない
まとめ部分で強引に製品やサービスを売り込むと、読者に不信感を与えてしまう可能性があります。特に、記事の内容と無関係な商品を無理に推すと、読者の興味を失わせる原因になります。
製品やサービスを紹介する際は、「この商品はこういう人におすすめ」「このサービスを使うことでこんなメリットがある」と、読者に寄り添った形で伝えることが大切です。過度な営業感を出さずに、読者の疑問や悩みに寄り添う形で提案することで、自然な購買行動につなげることができます。
本文を丸写ししない
まとめ部分で本文の内容をそのままコピー&ペーストしてしまうのはNGです。読者は記事をすでに読んでいるため、重複した情報を見ると「結局何が言いたいのか分からない」と感じてしまいます。
まとめの役割は、情報を再整理してポイントを簡潔に伝えることです。本文の流れを要約し、自分の言葉で端的に伝えることが求められます。SEOの観点でも、本文との重複表現が多いと検索評価に悪影響を及ぼす可能性があります。
抽象的・曖昧な言い回しをしない
まとめ部分で「なんとなく伝わる」ような抽象的な表現を使ってしまうと、読者は記事の要点を正確に理解できません。「しっかり考えましょう」「色々な方法があります」といった曖昧な表現では、読者の記憶に残らず、行動にもつながりにくくなります。
特にWeb記事では、結論を明確に伝えることが重視されます。曖昧な言い回しを避け、「〇〇すべき」「△△が効果的」といった具体性のある表現を意識することで、まとめの説得力が増し、読者の納得感も高まります。
論点がズレている・論理が飛躍している文章にしない
まとめで論点がズレていたり、唐突に新しい主張を展開してしまうと、読者に混乱を与えてしまいます。例えば、記事全体で「〇〇の重要性」を論じていたのに、まとめで「△△の活用が有効」と話題を変えてしまうと、論理の流れが途切れてしまいます。
まとめは、本文の主張を再確認し、読者に「何が大事だったのか」を明確に示す場です。論理の一貫性を保ち、記事全体の主旨と合致した内容にすることが、信頼性と読後感を高めるポイントです。
これから記事代行の外注を検討されている方は、記事制作代行NEOへご相談ください。記事制作代行NEOでは、業界最安水準の文字単価3円〜にて制作を行っております。
どの業者よりもリーズナブルかつ高品質な記事制作を行わせていただきます。キーワードの選定・執筆・ワードプレス入稿・リライト・SEO対策まで一括してご依頼いただけます。
まずはお気軽に以下のリンクよりご相談ください!
記事ジャンル別|おすすめのまとめ方
記事のまとめは、記事ジャンルによっても大きく異なります。
ここからは、ジャンル別のまとめ方の違いについて詳しく解説します。
ハウツー系記事のまとめ例
ハウツー系記事では、手順やノウハウを紹介した本文を踏まえて、最後に要点を箇条書きで整理すると効果的です。読者は「何をすればいいのか」を知りたいため、結論を明確に提示し、実践の一歩を後押しするようなまとめが求められます。
たとえば「この記事で紹介した〇つのステップは~」と総括し、あわせて注意点や成功のコツを添えると説得力が増します。また、「まずは〇〇から始めてみましょう」といった行動喚起を含めると、読者の実践につながります。
レビュー・比較記事のまとめ方
レビュー・比較記事では、本文で紹介した商品やサービスの特徴・違いを簡潔に再提示し、読者の判断を助けるまとめが重要です。各項目のメリット・デメリットを再度整理し、「結局どれがおすすめか」という結論をはっきり書くことが読者の満足度を高めます。
また、利用目的やユーザータイプ別に「〇〇な人にはA、△△ならB」といった提案型のまとめにすると、読者が自分に合った選択をしやすくなります。比較表やランキングを再掲するのも有効です。
コラム・体験談のまとめテクニック
コラムや体験談は感情に訴える内容が多いため、まとめでは「筆者の気づき」や「読者へのメッセージ」を中心に据えると響きます。経験から得た教訓や思いを簡潔に伝え、「共感」や「学び」で締めくくるのがポイントです。
「〇〇を通じて感じたのは〜でした」「あなたもぜひ〇〇を試してみてください」といった一文があると、読後感がよくなりシェアされやすい傾向があります。無理に結論を出すより、読者に余韻を与える言葉選びも大切です。
BtoBビジネス記事におけるまとめの工夫
BtoB向けの記事では、論理的で信頼性のあるまとめが求められます。本文で紹介したデータ・施策・導入効果などを根拠として要点を再整理し、「だからこの取り組みが必要だ」という結論につなげるのが基本です。
また、導入事例や活用シーンを簡単に再提示し、「自社でも応用可能」と思わせる構成にすると効果的です。CTAとして「資料請求はこちら」や「お問い合わせください」などを明示することで、商談につなげるアクションも促進できます。
記事制作は代行会社に依頼するのがおすすめ
記事制作を代行会社に依頼すると、質の高いコンテンツを安定的に提供できるためおすすめです。プロのライターが執筆することで、SEO対策が施された読みやすい記事を作成でき、検索順位の向上にもつながります。
また、社内で記事を作成する手間を省き、本業に集中できるのも大きなメリットです。さらに、代行会社には専門性の高いライターが在籍しているため、幅広いジャンルに対応できます。
コンテンツのクオリティを保ちつつ、効率よく運営したい場合に最適です。
記事代行なら記事代行NEOへ!

記事制作代行・運用代行であれば記事制作代行NEOへご相談ください。
記事制作代行NEOでは代行相場が文字単価5円以上が一般的なところ、文字単価3円より記事制作を請け負っております。
キーワードの選定、記事構成作成、WordPress入稿まで一括してご依頼いただけます。1からオウンドメディアを制作しようとお考えの方も、立ち上げからお任せいただくことが可能です。
まずはお気軽に以下のリンクより無料カウンセリングへお申し込みください。
これから記事代行の外注を検討されている方は、記事制作代行NEOへご相談ください。記事制作代行NEOでは、業界最安水準の文字単価3円〜にて制作を行っております。
どの業者よりもリーズナブルかつ高品質な記事制作を行わせていただきます。キーワードの選定・執筆・ワードプレス入稿・リライト・SEO対策まで一括してご依頼いただけます。
まずはお気軽に以下のリンクよりご相談ください!
記事のまとめでよくある質問
ここからは、記事のまとめでよくある質問について詳しく解説していきます。
まとめは何文字くらいが適切?
記事全体の長さにもよりますが、まとめは200〜400文字程度が適切とされています。要点を簡潔に整理しつつ、読者に内容を再確認させるのが目的なので、長すぎず短すぎないバランスが重要です。箇条書きや一文ごとの区切りも有効です。
本文が短い記事にもまとめは必要?
本文が短い場合でも、まとめは基本的に入れた方が良いです。記事の要点を整理し、読者の記憶に残りやすくするだけでなく、SEO上も評価されやすくなります。簡潔な一文でも良いので締めの言葉を用意しましょう。
AIでまとめ部分を作ってもいい?
AIを使ってまとめ部分を作成するのは有効ですが、必ず人の目で確認・修正することが重要です。AIは要点整理に優れていますが、文章が不自然だったり、論点がズレていることもあるため、仕上げは人間が行いましょう。
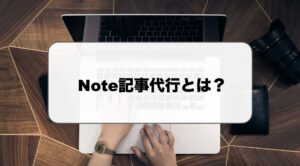
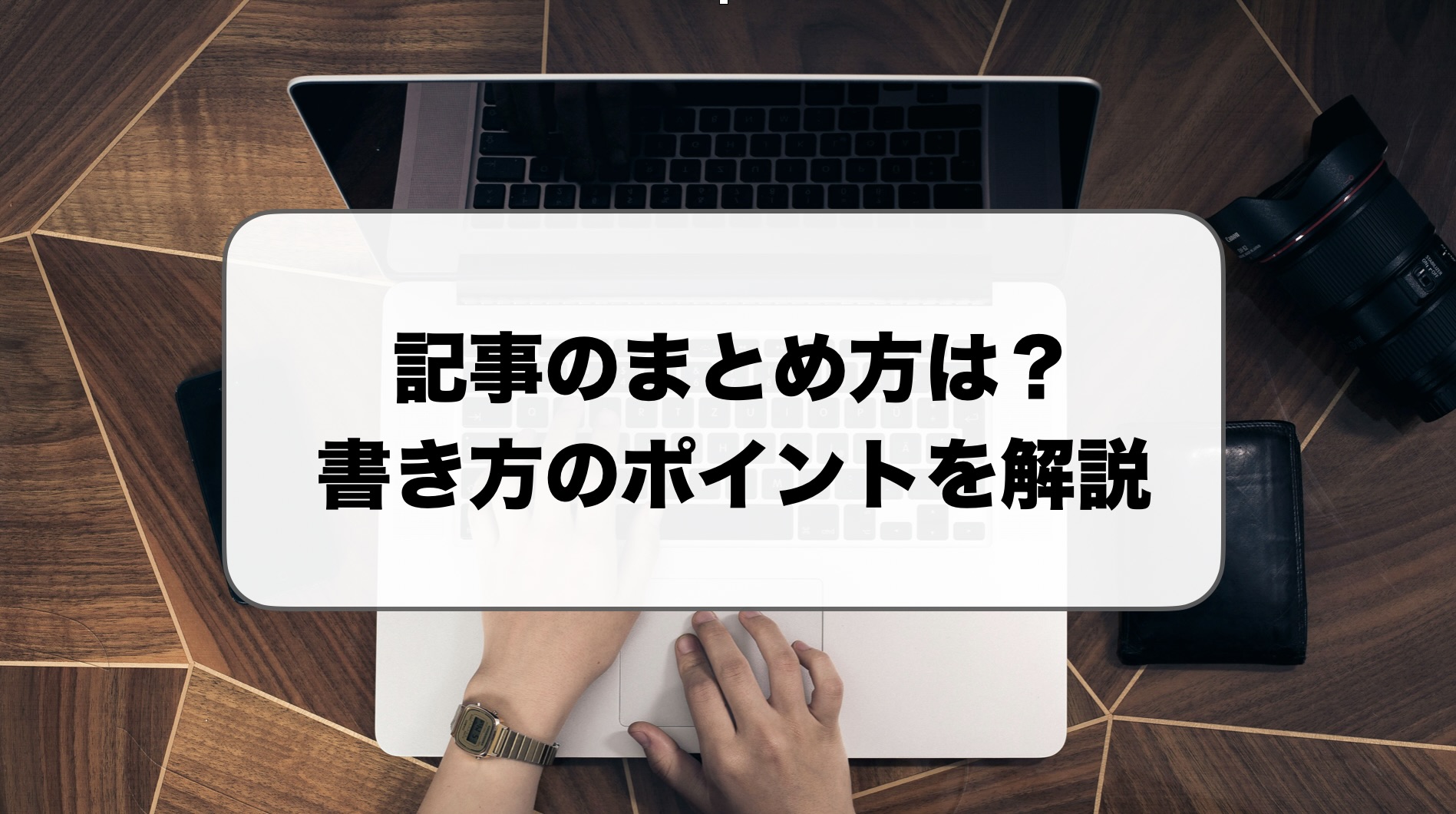
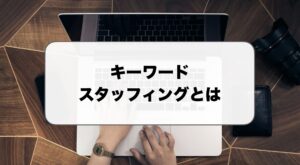

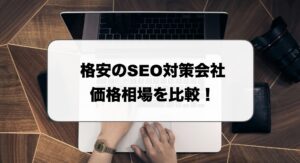
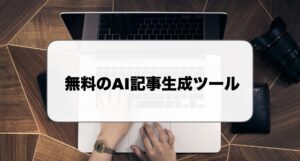

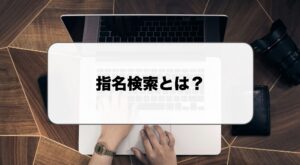
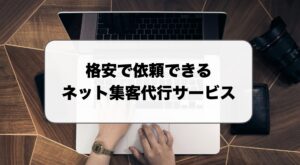

コメント