ネット記事の引用方法ってどうやるの?
正しい引用方法や書き方って?
このようにお悩みではないでしょうか。

1000社以上のSEO記事を作成。
SEO対策のことならなんでもご相談ください!
これから記事の外注を検討されている方は、記事制作代行NEOへご相談ください。記事制作代行NEOでは、業界最安水準の文字単価3円〜にて制作を行っております。
どの業者よりもリーズナブルかつ高品質な記事制作を行わせていただきます。キーワードの選定・執筆・ワードプレス入稿・リライト・SEO対策まで一括してご依頼いただけます。
まずはお気軽に以下のリンクよりご相談ください!
ネット記事の引用とは?

ここでは、ネット記事の引用の定義や、類似する「参照・出典・参考」との違いについて解説します。
ネット記事の引用とは
ネット記事の引用とは、他のウェブサイトや記事の一部を、適切なルールに従って自分の記事内に取り入れることです。引用には、明確な出典の記載、必要最小限の引用、主従関係の維持(自分の文章が主体であること)などのルールがあり、これらを守ることで著作権を侵害せずに使用できます。
たとえば、ニュース記事の一部を紹介する際は、記事の内容を丸ごと転載するのではなく、重要な部分のみを抜粋し、出典を明記することが求められます。適切な引用を行うことで、読者に信頼性の高い情報の提供が可能です。
参照・出典・参考それぞれの違い
「参照」「出典」「参考」は似た意味を持ちますが、それぞれ異なる役割を持ちます。「参照」は、他の情報をもとに自分の意見を述べる際に使われ、必ずしも原文をそのまま載せる必要はありません。
「出典」は、引用元を明確に示すために使われ、著作物の一部を抜粋する場合には必ず記載が必要です。「参考」は、記事の内容を考える際に影響を受けた情報を示すもので、具体的な文言をそのまま使うのではなく、情報の提供元を明示する役割があります。
適切に使い分けることで、記事の信頼性を高められるでしょう。
ネット記事の引用方法の種類
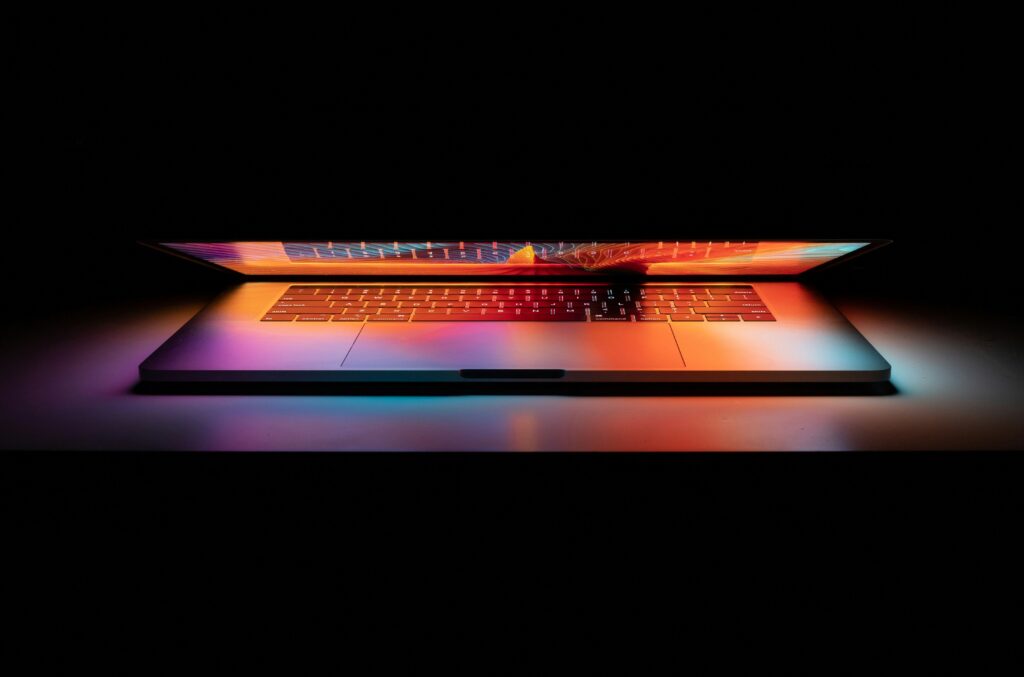
ネット記事を引用する際には、適切な方法を選ぶことが重要です。引用には「直接引用」「間接引用」「孫引き」などの種類があり、それぞれルールが異なります。ここでは、それぞれの特徴と正しい活用方法について解説します。
直接引用
直接引用とは、他のネット記事や書籍の文章を、そのままの形で自分の記事内に取り入れる方法です。文章を改変せず、必ず「」や『』などの引用符を用い、出典を明記する必要があります。
たとえば、「○○新聞によると、『○○の売上が前年比20%増加した』と報じられている」のように、原文を正確に記載します。直接引用は、原文の正確性を保つ必要がある場合や、専門家の発言や統計データをそのまま伝えたいときに有効です。
ただし、必要最小限の範囲にとどめ、自分の文章が主体となるようにするようにしましょう。
間接引用
間接引用とは、他のネット記事や書籍の内容を要約し、自分の言葉で言い換えて紹介する方法です。この場合、原文をそのまま使用せず、内容を正しく伝えつつ、独自の表現にすることが求められます。
たとえば、「○○新聞によると、今年の売上は前年比20%増加したという」といった形で表現します。間接引用では、引用符は不要ですが、出典を明記するのが基本です。
間接引用のメリットは、自分の文章に自然に組み込めることですが、内容を変えすぎると誤解を招く可能性があるため、正確に要約することが重要です。
孫引き
孫引きとは、ある情報源が別の情報源を引用している場合、その一次情報ではなく、二次情報をもとに引用することを指します。たとえば、Aのネット記事がBの書籍を引用している場合に、Bを直接読まずにAの記事を参考にするのが孫引きです。
この方法は、一次情報が手に入らない場合に便利ですが、情報が正確でない可能性があるため注意が必要です。理想的には、可能な限り一次情報を確認し、直接引用や間接引用を行うのが望ましいでしょう。
孫引きをする場合は、「○○(△△を引用)」といった形で、元の出典がどこなのかを明確に示すことが重要です。
これから記事の外注を検討されている方は、記事制作代行NEOへご相談ください。記事制作代行NEOでは、業界最安水準の文字単価3円〜にて制作を行っております。
どの業者よりもリーズナブルかつ高品質な記事制作を行わせていただきます。キーワードの選定・執筆・ワードプレス入稿・リライト・SEO対策まで一括してご依頼いただけます。
まずはお気軽に以下のリンクよりご相談ください!
ネット記事を引用しても良い条件とは?

ネット記事を引用する際には、著作権を侵害しないように一定の条件を守る必要があります。ここでは、それぞれの条件について詳しく解説します。
引用する記事が公表されていること
引用できる記事は、すでに公に発表されているものでなければなりません。未公開の情報や、限定的なアクセス権がある有料記事、会員限定コンテンツなどを許可なく引用すると、著作権の侵害となる可能性があります。
公表されているかどうかは、一般のユーザーが自由に閲覧できるかで判断されます。また、引用元が信頼できるかも重要なポイントです。
誤った情報を引用すると、自社のコンテンツの信頼性を損なうリスクがあるため、信頼できるメディアや公式情報を優先的に活用しましょう。
引用部分のURLを正しく記載すること
ネット記事を引用する際は、引用元のURLを正しく記載することが大切です。これにより、読者が引用元を直接確認でき、情報の透明性が保たれます。
また、出典を明示することで著作権者の権利を尊重し、引用の適法性を確保することにつながります。URLを記載しないと、情報の出どころが不明瞭になり、著作権違反とみなされる可能性があるため注意が必要です。
可能であれば、URLだけでなく記事タイトルや発信者名も併記し、正確な出典を示すことが望ましいでしょう。
引用記事と自社コンテンツが区別されていること
引用部分と自社コンテンツが明確に区別されていることも、適法な引用の条件です。引用した文章を自社のコンテンツと混ぜてしまうと、あたかも自社のオリジナルコンテンツであるかのように誤解される可能性があり、著作権侵害にあたることがあります。
そのため、引用部分には「」や『』などの引用符を使用する、フォントを変える、引用タグ(<blockquote>など)を使うといった方法で明確に区別しなければなりません。また、引用部分が記事の主役にならず、自社コンテンツが主体となるように構成することも重要なポイントです。
引用する著作者の著作権を侵害しないこと
ネット記事を引用する際には、著作権者の権利を侵害しないことが大前提です。引用は「著作権法第32条」に基づいて認められていますが、その範囲を超えると無断転載とみなされ、違法となる可能性があります。
特に、記事の大部分をそのまま掲載する、出典を明記しない、引用部分を主としたコンテンツにするなどの行為は、著作権侵害にあたるため注意が必要です。また、引用元の意図を歪める形で使用すると、名誉毀損や信頼性の低下を招く可能性があるため、正しく引用することが重要です。
引用部分は加工しない
引用する文章は、原則として加工せずにそのまま掲載する必要があります。誤字や脱字を修正したり、表現を変えたりすると、著作物の内容を改変したことになり、著作権侵害と判断される可能性が高いです。
引用する際は、原文を正確に写し、必要に応じて「」や『』を用いることで、引用部分が明確に分かるようにすることが重要です。ただし、長すぎる文章を部分的に省略する場合は、省略箇所があることを示す「…」を適切に使用し、文意が変わらないようにする必要があります。
引用する必然性があること
引用は、単なる転載ではなく、自分の主張を補強する目的で使用しなければなりません。たとえば、自分の記事で特定の主張を説明するために、信頼性の高いメディアの情報を引用する場合は、適法な引用とみなされます。
一方で、単に記事の内容を充実させるためだけに他の文章を引用するのは不適切です。引用の必然性が認められない場合、単なる盗用とみなされることもあるため、引用を行う際は「なぜこの情報が必要なのか」を明確にし、自分の文章が主体となるように構成することが重要です。
これから記事の外注を検討されている方は、記事制作代行NEOへご相談ください。記事制作代行NEOでは、業界最安水準の文字単価3円〜にて制作を行っております。
どの業者よりもリーズナブルかつ高品質な記事制作を行わせていただきます。キーワードの選定・執筆・ワードプレス入稿・リライト・SEO対策まで一括してご依頼いただけます。
まずはお気軽に以下のリンクよりご相談ください!
ネット記事の正しい引用方法

ネット記事を引用する際には、正しい方法で記載しなければなりません。ここでは、文章・書籍・SNS投稿・画像などの正しい引用方法について解説します。
文章を引用する際の書き方
ネット記事の文章を引用する際は、必ず「」や『』を用いて引用部分を明確に区別し、出典を記載することが必要です。例えば、「○○の記事によると、『●●』と述べられている。」のように表記します。
また、引用部分は必要最小限にとどめ、記事全体の主従関係を守ることが重要です。さらに、引用元のURLを明記し、読者が元の記事を確認できるようにすることで、信頼性を確保できます。
不適切な引用は著作権侵害につながるため、適切なルールを守ることが大切です。
参考文献の記載の仕方
ネット記事や書籍を参考にした場合、記事の最後に参考文献を記載することで、情報の信頼性を高めることができます。一般的な書き方として、「著者名(発行年)『記事タイトル』掲載サイト、URL、閲覧日」を記載するのが基本です。
例えば、「山田太郎(2024)『最新のPOSレジ事情』○○ニュース、https://○○.com(2025年3月20日閲覧)」のように書きます。参考文献を適切に記載すれば、読者に情報源を提示し、記事の正確性を保つことが可能です。
書籍の引用方法
書籍を引用する場合は、著者名・書籍名・出版社・発行年・該当ページを明記し、引用部分を「」や『』で囲みます。たとえば、「田中一郎(2023)『マーケティングの未来』○○出版、p.45」にあるように、『消費者の購買行動はデータに基づいて変化する』と述べられている。」のように表記します。
引用部分は改変せず、そのまま掲載することが重要です。また、書籍の全文を無断で掲載することは著作権侵害となるため、必要最小限の範囲で引用を行うことが求められます。
SNS投稿の引用方法
Twitter(X)やInstagram、FacebookなどのSNS投稿を引用する際は、投稿のURLを明記し、原文をそのまま引用する必要があります。
例えば、「○○さん(@username)がXで『新商品の発売が決定しました!』と投稿している。(https://twitter.com/username/status/123456789)」のように記載しましょう。
SNSの投稿は著作権の対象となるため、スクリーンショットの無断使用は避け、可能であれば投稿者の許可を得ることが望ましいです。
また、非公開アカウントの投稿や削除された投稿の引用は行わないよう注意しましょう。
画像の引用方法
画像を引用する場合は、著作権者の許可を得るか、引用の要件を満たしていることが必要です。引用時には、画像の出典を明記し、出典元のリンクを掲載するのが基本です。
例えば、「○○(2024)『POSレジの仕組み』○○サイトより引用(https://○○.com)」のように記載します。ただし、画像を編集・加工して使用することは原則として許可されていません。
また、著作権フリーの画像を利用する場合でも、ライセンス条件を確認し、適切なクレジット表記を行うことが重要です。
これから記事の外注を検討されている方は、記事制作代行NEOへご相談ください。記事制作代行NEOでは、業界最安水準の文字単価3円〜にて制作を行っております。
どの業者よりもリーズナブルかつ高品質な記事制作を行わせていただきます。キーワードの選定・執筆・ワードプレス入稿・リライト・SEO対策まで一括してご依頼いただけます。
まずはお気軽に以下のリンクよりご相談ください!
著作権を侵害してしまった場合のリスク

ネット記事の引用ルールを守らずに著作権を侵害すると、さまざまなリスクが発生します。軽度の違反であっても、法的トラブルに発展する可能性があるため、適切な引用を心がけることが重要です。ここでは、著作権侵害の主なリスクについて解説します。
法的訴訟に発展する可能性がある
著作権を侵害すると、著作権者から法的措置を取られる可能性があります。具体的には、引用元の著作権者が損害賠償を請求したり、記事の削除を求める訴訟を起こしたりすることも少なくありません。
裁判になった場合、違反者は金銭的な負担を強いられるだけでなく、企業や個人の信頼にも大きな影響を及ぼします。特に、意図的に無断転載を行った場合、賠償額が高額になるケースもあります。
訴訟リスクを避けるためにも、適切な引用ルールを守り、事前に著作権者の許可を得ることが重要です。
自社サイトを閉鎖しなければならない可能性がある
著作権侵害が発覚し、繰り返し違反を指摘された場合、運営するサイトの閉鎖を求められることがあります。著作権者や関連団体から警告を受け、違反が続くと、検索エンジンからの除外やサーバー提供会社からの契約解除といった措置が取られることも多いです。
特に、無断転載が頻繁に行われているサイトは、訴訟リスクだけでなく、サイト運営そのものが困難になる可能性が高まります。著作権を適切に守らなければ、ビジネスやメディアの存続に大きな影響を及ぼすことになるため、注意が必要です。
刑事罰を受ける可能性がある
著作権侵害が悪質な場合、民事責任だけでなく刑事罰の対象となることがあります。日本の著作権法では、意図的に著作権を侵害した場合、10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金、もしくはその両方が科される可能性があります。
また、法人として著作権侵害を行った場合、最大3億円の罰金が課されるケースもゼロではありません。特に、他人のコンテンツを無断で商用利用した場合や、著作権者の警告を無視して転載を続けた場合、刑事告訴される可能性が高くなります。
知らなかったでは済まされないため、著作権の知識を正しく持ち、法的リスクを回避することが重要です。
これから記事の外注を検討されている方は、記事制作代行NEOへご相談ください。記事制作代行NEOでは、業界最安水準の文字単価3円〜にて制作を行っております。
どの業者よりもリーズナブルかつ高品質な記事制作を行わせていただきます。キーワードの選定・執筆・ワードプレス入稿・リライト・SEO対策まで一括してご依頼いただけます。
まずはお気軽に以下のリンクよりご相談ください!
ネット記事を引用するメリットは?
ここでは、ネット記事を引用するメリットについて解説します。
自社記事の専門性や信頼性を高めることができる
ネット記事を引用することで、記事の専門性や信頼性を向上させられる点がメリットです。特に、公的機関や権威あるメディアの情報を適切に引用することで、読者にとって信頼できる情報源として認識されやすくなります。
また、専門家の意見や統計データを引用することで、自社の主張を補強し、説得力を高めることができます。ただし、引用部分と自社のオリジナルコンテンツのバランスを考え、引用が記事の主役にならないようにすることが重要です。
適切な引用を行うことで、記事の価値を向上させ、読者の信頼を獲得できます。
外部リンクの設置でグーグル評価が高まる
ネット記事を引用する際に外部リンクを設置することで、Googleの評価を向上させることが可能です。検索エンジンは、権威のあるサイトと関連性の高いリンクを持つページを高く評価する傾向があります。
特に、信頼性のあるニュースサイトや公的機関のデータを引用し、適切にリンクを設定することで、検索順位の向上につながります。ただし、低品質なサイトや信頼性の低い情報源にリンクすると、逆に評価が下がる可能性があるため、引用元の選定は慎重に行うことが大切です。
適切な引用と外部リンクの活用は、SEO対策の一環として有効な手段となります。
ユーザーの滞在率が高まる
ネット記事を適切に引用することで、読者が記事に興味を持ち、サイト内での滞在時間を延ばすのに効果的です。引用によって専門的な情報や興味深いデータを提供できるため、読者は記事の内容を深く理解しやすくなります。
また、引用部分を補足する形で関連情報を提供することで、ユーザーが次のコンテンツへとスムーズに移動し、サイトの回遊率向上にもつながります。ユーザーの滞在時間が長くなれば、検索エンジンからの評価も高まり、サイトのSEO効果を強化することが可能です。
適切な引用を活用することで、読者の満足度とサイトの価値を高められるでしょう。
これから記事の外注を検討されている方は、記事制作代行NEOへご相談ください。記事制作代行NEOでは、業界最安水準の文字単価3円〜にて制作を行っております。
どの業者よりもリーズナブルかつ高品質な記事制作を行わせていただきます。キーワードの選定・執筆・ワードプレス入稿・リライト・SEO対策まで一括してご依頼いただけます。
まずはお気軽に以下のリンクよりご相談ください!
引用なしで使うなら「フリー画像」も検討しよう
引用せずに記事を作成する場合にはフリー画像の利用もおすすめです。
ここでは、フリー画像の概要について解説します。
商用利用OKなものか事前に確認しておく
フリー画像といっても、すべてが商用利用可能とは限りません。個人のブログで使用する場合と、企業サイトやECサイトなどの商用目的で使用する場合とでは、利用規約が異なることがあります。
中には「非営利利用のみ可」「教育目的に限る」といった条件付きの画像も存在するため、事前に利用規約を確認することが非常に重要です。商用利用不可の画像を企業サイトなどで使ってしまうと、後々著作権侵害と判断され、トラブルになる可能性も。トラブル回避のためにも、「商用利用可」「クレジット不要」などの条件が明記されている画像を選ぶよう心がけましょう。
加工してもOKか確認しておく
フリー画像の中には、ダウンロードしてそのまま使用することは許可されていても、加工(トリミング・色変更・合成など)を禁止しているものもあります。特にイラスト素材や人物写真の場合、クリエイターの意図や肖像権の観点から、改変を制限しているケースが多いです。
コンテンツに合わせて画像を自由に編集・加工したい場合は、ライセンス上「加工可」と明記されている素材を選ぶ必要があります。また、画像提供サイトによって規定が異なるため、使用前に「利用ガイドライン」や「FAQ」を必ずチェックすることが、安全な運用につながります。
クレジット表記が必須の場合もある
一部のフリー画像は、使用自体は無料でも「クレジット(著作権者名や提供元の明記)が必要」と定められている場合があります。たとえば、「© 写真AC」や「画像提供:Pixabay」といった表記をページのどこかに記載しなければならないケースです。これを怠ると、利用規約違反とされ、トラブルの原因になることもあります。
特に商用利用時には厳格にチェックされやすいため、画像を使う前にクレジット表記の有無・形式を確認しておくことが大切です。クレジット表記不要の画像を探している場合は、その条件でフィルター検索できるサイトを利用するのがおすすめです。
例えフリー画像であっても著作権がある
「フリー画像」という言葉は「著作権がない」と誤解されがちですが、実際には著作権を放棄していないケースが大半です。多くのフリー素材は、著作権者が「一定の条件下で使用を許可している」だけであり、著作権自体は保持されています。
そのため、利用規約に反した使い方(無断転載・無断販売・禁止用途での利用など)をすれば、著作権侵害とみなされ法的措置を取られる可能性もあります。また、画像内に人物が写っている場合は肖像権の問題も絡んでくるため、より慎重な扱いが必要です。フリーであっても、著作物であるという認識を忘れずに使用しましょう。
記事代行なら記事代行NEOへ!
記事制作代行・運用代行であれば記事制作代行NEOへご相談ください。
記事制作代行NEOでは代行相場が文字単価5円以上が一般的なところ、文字単価3円より記事制作を請け負っております。
キーワードの選定、記事構成作成、WordPress入稿まで一括してご依頼いただけます。1からオウンドメディアを制作しようとお考えの方も、立ち上げからお任せいただくことが可能です。
まずはお気軽に以下のリンクより無料カウンセリングへお申し込みください。
これから記事の外注を検討されている方は、記事制作代行NEOへご相談ください。記事制作代行NEOでは、業界最安水準の文字単価3円〜にて制作を行っております。
どの業者よりもリーズナブルかつ高品質な記事制作を行わせていただきます。キーワードの選定・執筆・ワードプレス入稿・リライト・SEO対策まで一括してご依頼いただけます。
まずはお気軽に以下のリンクよりご相談ください!
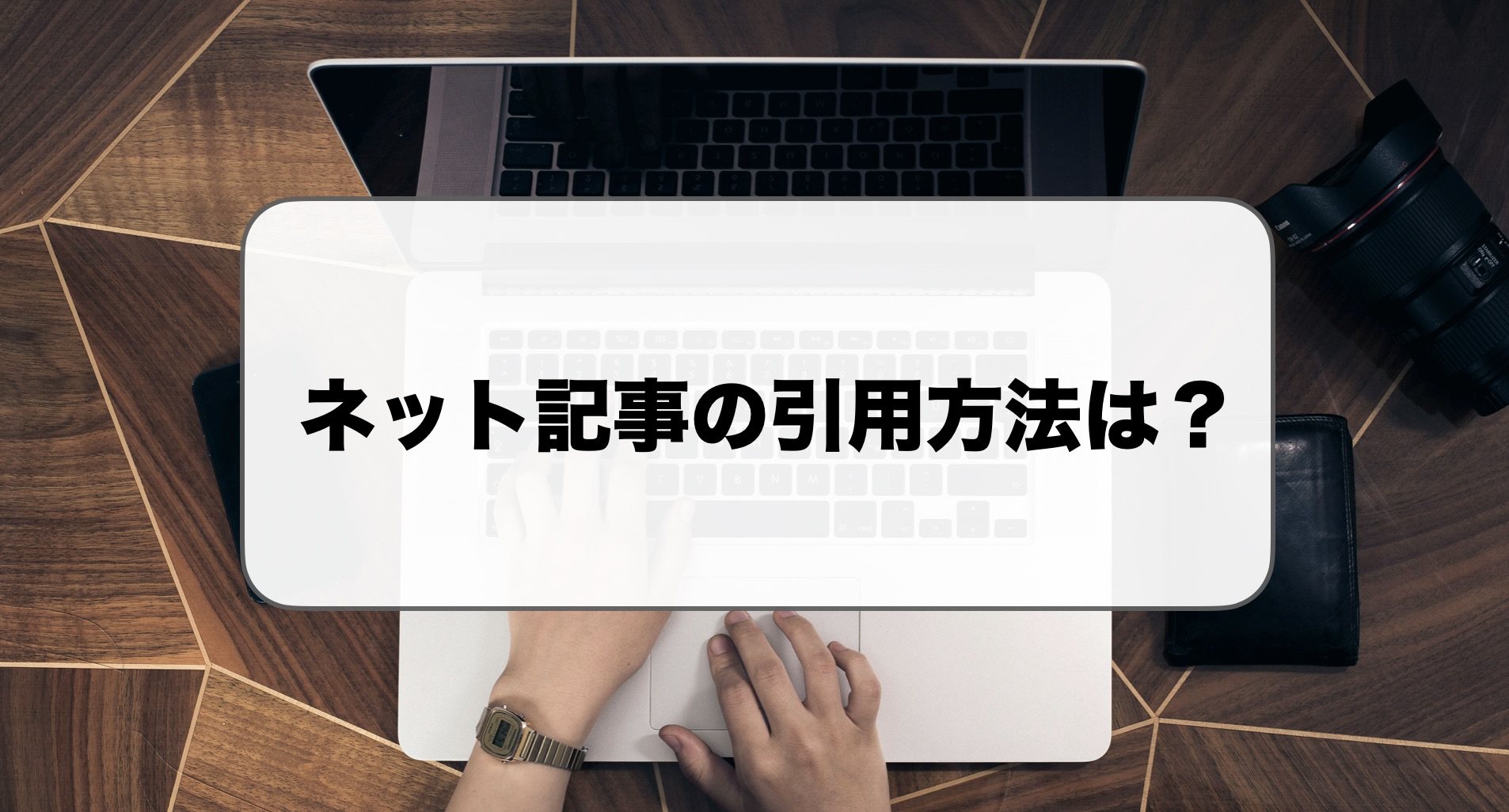
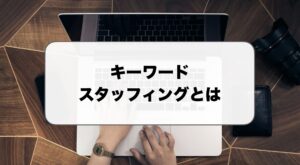

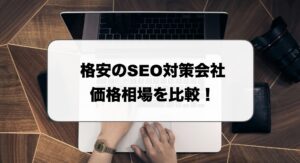
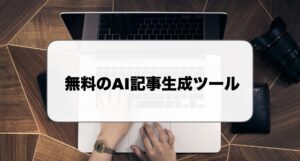
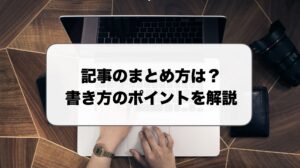

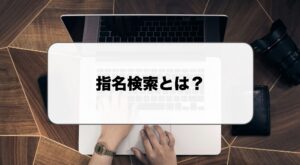
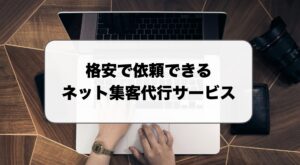
コメント