トップレベルドメインとは?
トップレベルドメインはどう選べばいいの?
このようにお悩みではないでしょうか。

1000社以上のSEO記事を作成。
SEO対策のことならなんでもご相談ください!
これから記事の外注を検討されている方は、記事制作代行NEOへご相談ください。記事制作代行NEOでは、業界最安水準の文字単価3.5円〜にて制作を行っております。
どの業者よりもリーズナブルかつ高品質な記事制作を行わせていただきます。キーワードの選定・執筆・ワードプレス入稿・リライト・SEO対策まで一括してご依頼いただけます。
まずはお気軽に以下のリンクよりご相談ください!
トップレベルドメインとは

トップレベルドメイン(TLD)とは、インターネット上のドメイン名のうち、最も右側に位置する部分を指します。 たとえば「example.com」の場合、「.com」がトップレベルドメインです。TLDは大きく分けて「分野別(gTLD)」と「国別(ccTLD)」の2種類があります。前者には「.com(商業)」「.net(ネットワーク)」「.org(非営利)」などがあり、誰でも取得可能です。
一方、ccTLDは「.jp(日本)」「.uk(イギリス)」など国や地域を表し、取得に制限がある場合もあります。さらに近年では「.shop」や「.tokyo」など新しいTLDも登場し、企業や個人がブランドや用途に応じて選べるようになっています。TLDはウェブサイトの信頼性やブランディングにも関わる重要な要素です。
トップレベルドメインの種類

ここでは、トップレベルドメインの種類について解説します。
gTLD(ジェネリックトップレベルドメイン)
gTLD(ジェネリックトップレベルドメイン)は、国や地域に関係なく誰でも取得できる汎用的なトップレベルドメインです。代表的な例には「.com(商業)」「.net(ネットワーク)」「.org(非営利団体)」などがあります。
これらはインターネットの初期から使われており、現在でも多くのウェブサイトに利用されています。gTLDは、ドメインの使用目的によってある程度の意味合いがありますが、登録に厳格な制限はないため、個人や企業を問わず自由に取得可能です。信頼性や認知度の高い「.com」は特に人気があり、ビジネス用途では定番とされています。ドメイン選定においては、gTLDの種類やブランドとの親和性を考慮することで、訪問者に安心感を与える効果も期待できます。
ccTLD(国別コードトップレベルドメイン)
ccTLD(国別コードトップレベルドメイン)は、各国や地域ごとに割り当てられた2文字のトップレベルドメインです。たとえば「.jp(日本)」「.us(アメリカ)」「.de(ドイツ)」「.cn(中国)」などがあります。国や地域ごとにドメイン登録のルールが異なり、取得に住所や法人登記などの条件が必要な場合もあります。ccTLDを利用することで、検索エンジンに対してその国向けのサイトであることを示すことができ、地域に特化したSEO対策としても有効です。
また、ユーザーにも「このサイトは国内企業の運営だ」といった安心感を与えることができます。日本国内でのビジネスや情報発信を行う場合、「.jp」や「.co.jp」などのccTLDは非常に相性の良い選択肢です。
新gTLD(新しいジェネリックTLD)
新gTLD(New gTLD)は、2012年からICANNによって新たに導入されたジェネリックトップレベルドメインで、「.shop」「.tokyo」「.app」などが代表例です。これらは、企業や団体、都市名、業種などに特化したものが多く、ブランドやサービスの個性をより明確に表現することができます。たとえば「.hotel」や「.cafe」など業種に関連したTLDを使えば、訪問者に一目で業態を伝えることが可能です。
また、既存のgTLD(例:.com)がすでに埋まっている場合でも、希望する名前で取得しやすいというメリットがあります。ただし、新gTLDはまだ認知度が低いものも多く、ユーザーにとってなじみが薄い場合があります。そのため、選ぶ際はブランディングやターゲット層との親和性を慎重に検討する必要があります。
sTLD (スポンサー付きトップレベルドメイン)
sTLD(Sponsored Top-Level Domain)は、特定の業界団体や組織がスポンサーとなり、その分野の関係者のみが登録できる制限付きのトップレベルドメインです。代表例としては「.edu(教育機関)」「.gov(政府機関)」「.museum(博物館)」「.aero(航空業界)」などがあります。
これらのドメインは、登録要件が厳格に定められており、例えば「.edu」は主に米国の認可を受けた高等教育機関のみが取得可能です。sTLDは、限定された用途で使用されることにより、信頼性や権威性が高く評価される傾向にあります。たとえば「.gov」ドメインであれば、公的機関が運営していることが明白であり、情報の信ぴょう性も高く見られます。信頼性が重要な分野では、sTLDの活用が有効な手段となります。
.arpa ドメイン
「.arpa」ドメインは、通常のウェブサイト用とは異なり、インターネットの技術的インフラを支える特別な用途に使われるトップレベルドメインです。元々は「Address and Routing Parameter Area」の略で、インターネット黎明期にネットワーク移行の一時的措置として設けられましたが、現在ではDNS逆引き(IPアドレスからドメイン名を調べる)など、技術運用に不可欠な用途に限定されています。
一般の企業や個人が登録・利用することはできません。例として、IPv4アドレスの逆引きに使用される「in-addr.arpa」や、IPv6の「ip6.arpa」があります。「.arpa」ドメインはICANNとIANAによって管理されており、インターネットの安定運用において極めて重要な役割を果たしている、技術基盤のための特殊なTLDです。
tTLD(テスト用TLD)
tTLD(テスト用トップレベルドメイン)は、インターネット標準技術の開発・試験目的で利用される、仮想的なTLDのことです。代表的なのが「.test」で、このドメインは実際のインターネット上では利用されておらず、DNSに登録されていません。そのため、アプリケーションやブラウザ、ネットワーク機器の動作検証、開発環境の構築などにおいて安全に使うことができます。
また、他にも「.example」「.invalid」「.localhost」なども予約済みドメインとして、文書や技術的サンプル用に指定されています。tTLDは、開発中に誤って外部の実ドメインにアクセスしてしまうリスクを回避できる点で有用です。これらのドメインはICANNによって予約されており、現実のインターネットには存在しないことが保証されている、試験専用のTLDです。
これから記事の外注を検討されている方は、記事制作代行NEOへご相談ください。記事制作代行NEOでは、業界最安水準の文字単価3.5円〜にて制作を行っております。
どの業者よりもリーズナブルかつ高品質な記事制作を行わせていただきます。キーワードの選定・執筆・ワードプレス入稿・リライト・SEO対策まで一括してご依頼いただけます。
まずはお気軽に以下のリンクよりご相談ください!
人気のトップレベルドメインランキング

ここでは、トップレベルドメインの人気ランキングについて解説します。
.com
「.com」はインターネット全体で最も普及しているトップレベルドメインで、全ウェブサイトの約43.7〜44.4%が利用しています。元々は商業用に設計されたTLDですが、現在では企業や個人ブログ、eコマースなど、あらゆる用途に幅広く利用されています。その普及率の高さから、ユーザーの信頼獲得にも有利であり、SEO面でも最も権威あるTLDとされています。登録数では約1.55億件(2025年初頭)と圧倒的であり 、ドメイン所有の選択肢として優先されることが多いTLDです。
.net
「.net」は元来ネットワーク関連企業向けの汎用gTLDとして設計され、インターネットインフラや技術系サイトに多く利用されました。現在では制限なく誰でも取得可能で、全ウェブサイトの約2.3%が.netを使用。登録数は約1,234万件(2025年初頭)に達しています 。技術ベンチャーやインフラ系企業が選ぶ傾向があり、.comが取得できない場合の信頼性ある代替手段として有用です。gTLDとして長い歴史を持ち、安定性や認知度も高いTLDです 。
.jp
「.jp」は日本を表す国別コードトップレベルドメイン(ccTLD)で、1986年に導入され、2025年2月時点で約178万のドメインが登録。日本国内に住所を持つ個人・法人のみが第二レベルとして登録可能。地域密着型サイトや日本の企業・店舗では信頼向上やSEOでの地域優位性が得られるため人気があります。さらに「co.jp」「ac.jp」「or.jp」など用途別の第三レベルドメインも発達し、日本に根ざしたWeb展開に強力な基盤を提供します。
.org
「.org」は“organization”の略で、1985年に設立された歴史あるgTLDです。非営利団体、コミュニティ、教育機関などが多く使用し、実際には全ウェブサイトの約4.1%が使用中。日本国外では約1,120万件の登録があり 、その中には有名なオープンソースや公益系プロジェクトが多数含まれます。認知度と信頼性が高く、ブランディング面でも「非営利性」や「公共性」を強調したい団体に適するTLDです。
.xyz
「.xyz」は2014年に導入された比較的新しいgTLDで、アルファベットの最後を示す汎用性の高いドメインです 。2025年初頭には約380万件が登録されました 。Alphabet社(Googleの親会社)が「abc.xyz」を採用したことで知名度が上がり、スタートアップやテック企業の間で「革新性やフレキシブルさ」を示すドメインとして人気です。ただし、フィッシング等の悪用報告もあり、信頼性の観点からは慎重な選定が求められます 。
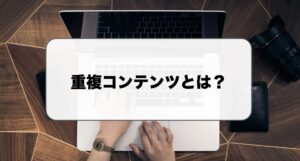
これから記事の外注を検討されている方は、記事制作代行NEOへご相談ください。記事制作代行NEOでは、業界最安水準の文字単価3.5円〜にて制作を行っております。
どの業者よりもリーズナブルかつ高品質な記事制作を行わせていただきます。キーワードの選定・執筆・ワードプレス入稿・リライト・SEO対策まで一括してご依頼いただけます。
まずはお気軽に以下のリンクよりご相談ください!
SEOとトップレベルドメインの関係性
トップレベルドメイン(TLD)は、直接的にSEOランキングへ大きな影響を与える要素ではないものの、信頼性やクリック率といった間接的な要因に関与します。たとえば、一般に広く知られている「.com」や「.jp」はユーザーからの信頼が高く、クリックされやすいため、結果的にSEO効果が高まる傾向があります。
また、ccTLD(国別ドメイン)は地域SEOに効果的で、特定国での検索順位向上が見込まれます。一方で、「.xyz」や「.info」などの一部TLDはスパムサイトに使われやすく、検索エンジンやユーザーに警戒される可能性があります。つまり、TLDは検索順位を左右するわけではないものの、信頼性・ブランド価値・クリック率といったSEOに関わる周辺要素に間接的な影響を与える重要な選定要素です。
トップレベルドメインを選ぶときのポイント

ここでは、トップレベルドメインを選ぶときのポイントについて解説します。
まずはgTLDを探す
ドメインを選ぶ際は、まず「.com」「.net」「.org」などのgTLD(ジェネリックトップレベルドメイン)から検討するのが基本です。これらは長い歴史と高い認知度があり、ユーザーに安心感を与えやすいドメインです。特に「.com」は全世界で最も多く使用されており、ビジネスやサービス展開において信頼の象徴とされることもあります。
また、gTLDはSEO面でも中立的かつ安定した評価を受けやすく、特定の国や用途に縛られずに運用できるのもメリットです。希望するドメイン名が既に取得されていることも多いですが、その場合は別のgTLD(例:「.net」「.info」など)を検討することで、ブランディングを維持しつつ選択肢を広げることが可能です。まずgTLDを中心に選定することは、ドメイン戦略の出発点として最も合理的です。
自社のサービスやブランドとの整合性を意識する
ドメイン名とTLDは、企業やサービスの印象を左右する重要な要素です。TLDを選ぶ際には、自社の業種やブランドコンセプトと整合性が取れているかを重視する必要があります。
たとえば、IT企業であれば「.tech」や「.io」、飲食店であれば「.cafe」や「.restaurant」といった新gTLDを使うことで、業種との親和性をアピールできます。また、ブランディングの一貫として、TLDが視覚的・語感的にも社名やサービス名と一体化していることが望ましいです。これはユーザーの記憶に残りやすく、SNSや広告でも統一感を持たせることができます。
一方、業種と無関係なTLDを選ぶと、怪しさや信頼性の欠如につながる可能性があるため注意が必要です。自社の価値や訴求ポイントと一致したTLD選定が、マーケティング全体の効果にも好影響を与えます。
ターゲット地域に合わせてTLDを選ぶ
ドメイン戦略では、ターゲットとする地域や市場に適したTLDを選ぶことが重要です。たとえば、日本市場をメインにするなら「.jp」や「.co.jp」などのccTLD(国別コードトップレベルドメイン)を使うことで、検索エンジンに対して「日本向けのサイト」であることを明確に示せます。
これにより地域SEOに強くなり、現地ユーザーの検索結果に表示されやすくなります。また、ローカルユーザーにとっても親近感や信頼感が生まれやすく、クリック率や滞在時間の向上が期待されます。海外市場向けには「.us」「.uk」「.cn」など該当地域のTLDを選ぶと効果的です。一方で、グローバル展開を視野に入れる場合は、特定の国に限定されない「.com」や「.net」などのgTLDを使うことで、国際的な信頼性を担保することができます。
将来的なドメイン運用や拡張性も考慮する
ドメインは短期的な使用だけでなく、長期的な事業成長やブランド展開を見据えて選ぶことが重要です。たとえば、当初は日本国内での展開を想定して「.jp」を使用していたとしても、将来的に海外進出を考えるなら「.com」などの汎用性の高いTLDの方が適しています。
また、新しいサービスやサブブランドを立ち上げる場合に、同一ブランドのバリエーション(例:subdomain.example.com)や他のTLD(example.netなど)を確保しておくことで、他者に先取りされるリスクを回避できます。ドメイン運用における拡張性とは、ブランドの一貫性を維持しながら多様な展開が可能な構造を持っているかどうかです。特に商標やSNSアカウントとの整合性も含め、将来的なマーケティング展開まで想定したドメイン戦略が求められます。
TLDの入手性や費用も確認する
TLDの選定においては、その入手のしやすさや年間の維持費も重要な検討材料です。たとえば「.com」や「.net」は人気が高いため希望するドメイン名がすでに登録されていることが多く、プレミア価格でしか取得できないケースもあります。
一方で「.xyz」や「.online」などの新gTLDは取得しやすく、初年度が格安で提供されていることもありますが、2年目以降の更新費用が高額になる場合もあるため、長期的なコストを事前に確認しておく必要があります。また、一部のTLDでは登録に条件(国内住所の有無など)がある場合もあります。費用と管理の面からも、TLD選びは単なる見た目やイメージだけでなく、実務上の負担や将来のリスクも含めて慎重に検討すべきポイントです。
これから記事の外注を検討されている方は、記事制作代行NEOへご相談ください。記事制作代行NEOでは、業界最安水準の文字単価3.5円〜にて制作を行っております。
どの業者よりもリーズナブルかつ高品質な記事制作を行わせていただきます。キーワードの選定・執筆・ワードプレス入稿・リライト・SEO対策まで一括してご依頼いただけます。
まずはお気軽に以下のリンクよりご相談ください!
トップレベルドメインを選ぶ際の注意点

ここでは、トップレベルドメインを選ぶときの注意点について解説します。
安易に安価なTLDを選ばない
TLD選びで初期費用の安さに惹かれて「.xyz」や「.top」などの格安ドメインを選ぶのは要注意です。これらのTLDは初年度が数十円〜数百円と非常に安価ですが、2年目以降の更新料が高額になるケースも多く、長期運用でのコスト増につながります。また、格安TLDはスパムサイトや不正利用の温床になりやすく、検索エンジンやユーザーからの信頼性が低下する傾向もあります。
GoogleはTLDだけで順位を決めることはないとしていますが、TLDに対するユーザーの印象やクリック率はSEOに間接的に影響します。そのため、安さだけで選ぶとブランドイメージに悪影響を及ぼすことも。信頼性・ブランド戦略・更新コストを含めて、総合的に判断したうえでTLDを選ぶことが大切です。
長いトップレベルドメインを選ばない
TLDには短いもの(例:.com、.jp)から比較的長いもの(例:.international、.photography)までさまざまありますが、できる限り短く覚えやすいTLDを選ぶことが望ましいです。TLDが長くなると、URL自体も長くなり、ユーザーが入力ミスを起こしやすくなるほか、SNSや広告媒体での表示スペースを圧迫する原因にもなります。また、長いTLDは視覚的にも印象に残りにくく、信頼性やプロフェッショナリズムに欠ける印象を与えることがあります。特に、ブランド名とTLDを合わせたドメイン名が長すぎると、ユーザーの記憶にも残りにくくなり、再訪問やシェアの妨げになります。短く、わかりやすく、発音しやすいTLDを選ぶことで、ユーザー体験とブランド認知を向上させることができます。
マイナーなトップレベルドメインは選ばない
TLDには多くの選択肢がありますが、あまり認知されていないマイナーなTLD(例:.bid、.review、.gdnなど)は避けた方が無難です。理由は主に3つあります。第一に、ユーザーがそのTLDに馴染みがなく、信頼性に不安を感じること。第二に、マイナーTLDはスパムや詐欺サイトでの利用率が高い傾向があり、セキュリティ警戒されやすいこと。第三に、企業ブランドやSEO戦略上の影響です。
たとえば、GoogleがTLDによって検索順位を変えることは基本的にないとしていますが、ユーザーのクリック率や直帰率がTLDによって変わる可能性があります。こうした要素が結果的にSEOやブランディングに悪影響を及ぼすこともあります。知名度が高く、信頼性のあるTLDを選ぶことが、安定したWeb運用に繋がります。
これから記事の外注を検討されている方は、記事制作代行NEOへご相談ください。記事制作代行NEOでは、業界最安水準の文字単価3.5円〜にて制作を行っております。
どの業者よりもリーズナブルかつ高品質な記事制作を行わせていただきます。キーワードの選定・執筆・ワードプレス入稿・リライト・SEO対策まで一括してご依頼いただけます。
まずはお気軽に以下のリンクよりご相談ください!
ドメインを検索して申し込む方法

ここでは、トップレベルドメインを検索して申し込む方法について解説します。
ステップ1: ドメイン取得サービス(例:お名前.com、ムームードメインなど)にアクセスする
まず、ドメインを取得するには「レジストラ」と呼ばれるドメイン登録サービスを利用します。日本で代表的なサービスには「お名前.com」「ムームードメイン」「さくらのドメイン」「Xserverドメイン」などがあります。
これらのサイトは、ドメイン検索・購入・管理をすべてオンラインで完結でき、初心者でも使いやすいUIが整っています。サービスによって取り扱っているトップレベルドメイン(TLD)の種類や価格、サポート体制、オプション機能が異なるため、自分の用途や予算に合ったものを選ぶとよいでしょう。
ステップ2: 希望するドメイン名を検索窓に入力し、使用可能か確認する
レジストラのサイトにアクセスしたら、まずは取得したいドメイン名(例:www.○○○.com)の「○○○」部分を検索窓に入力し、使用可能かどうかを調べます。入力後、検索ボタンをクリックすると、さまざまなトップレベルドメイン(.com、.jp、.netなど)での空き状況が一覧で表示されます。既に他のユーザーに登録されている場合は「取得不可」や「プレミアムドメイン(高額)」と表示され、取得できません。
一方、「取得可能」と表示されていれば、選択して申し込みに進むことができます。この段階では、自社名・サービス名・ブランド名に近い綴りが利用できるかを確認し、候補を複数用意しておくとスムーズです。また、誤字や混同されやすい類似ドメインの確認も、ブランディング上重要です。
ステップ3: 使用可能なドメインの中から希望のトップレベルドメイン(.com、.jpなど)を選ぶ
検索結果には、使用可能な複数のトップレベルドメイン(TLD)が表示されます。たとえば「.com」「.net」「.jp」「.info」「.tokyo」などから選べますが、ビジネス用途で信頼性を重視するなら「.com」や「.jp」が定番です。TLDによって年間の料金、更新料、取得条件が異なるため、価格や用途をよく確認しましょう。
また、SEOやブランディングの観点から、自社の業種やターゲット地域に合ったTLDを選ぶことが大切です。すでに他社が主要TLDを取得している場合は、代替候補(例:「.biz」「.net」)を検討することもあります。TLDを選ぶ段階で、将来のブランド展開や複数サイト運営も視野に入れておくと、より戦略的なドメイン運用が可能になります。
ステップ4: カートに追加し、必要に応じてオプション(Whois情報公開代行など)を選択する
希望のドメインとTLDを選択したら、ショッピングカートに追加し、必要なオプションを設定します。代表的なオプションのひとつが「Whois情報公開代行」で、ドメイン所有者の名前や住所などの個人情報を外部に公開せず、代行業者の情報でマスクする仕組みです。個人利用や小規模事業では、プライバシー保護の観点から非常に有効です。
他にも、メールアドレス作成機能、SSL証明書の同時申込、サーバーとのセット割など、レジストラによってさまざまなオプションがあります。不要なオプションを外すことで費用を抑えることもできますが、セキュリティや実務上必要な機能は慎重に選びましょう。内容を確認したら「申し込む」「次へ」などのボタンを押して次のステップに進みます。
ステップ5: ユーザー登録またはログインを行う
ドメインの購入手続きを進めるには、利用するレジストラでの会員登録(ユーザーアカウント作成)が必要です。既にアカウントを持っている場合はログインし、初めての方はメールアドレス、パスワード、氏名、住所、電話番号などを入力して登録します。
これらの情報は、Whois情報や今後の契約・請求・更新通知の連絡先として使用されるため、正確に入力する必要があります。法人での利用の場合は、会社名や担当者名なども求められる場合があります。登録後は、マイページや管理画面からドメインの管理・設定変更が可能になります。セキュリティ強化のため、二段階認証やSMS認証が用意されているレジストラもあるため、設定しておくと安心です。
ステップ6: 支払い方法を選択し、ドメイン取得を完了する
ユーザー登録が完了したら、購入内容の確認と支払い手続きに進みます。支払い方法は、クレジットカード・銀行振込・コンビニ払い・PayPayなど、レジストラによって複数用意されています。
基本的には1年単位での契約が多いですが、2〜10年の長期契約が可能な場合もあり、長期割引や自動更新の設定ができるサービスもあります。料金にはドメイン取得費用のほか、オプション(Whois代行、SSLなど)の費用が加算されるため、明細を確認してから決済を行いましょう。支払い完了後、通常数分~数時間以内にドメインが有効となり、登録したメールアドレスに「取得完了のお知らせ」が届きます。この時点で正式にそのドメインの所有権があなたに移ります。
ステップ7: 登録者情報やネームサーバー、DNS、SSL設定などを必要に応じて行う
ドメイン取得が完了したら、サイトの運用に向けて必要な初期設定を行います。まずはWhois登録情報が正しく反映されているか確認し、ネームサーバー(DNS)を、使用するレンタルサーバーのものに変更します。これにより、ドメインとサーバーが紐付き、Webサイトが表示できるようになります。
また、メール機能を使う場合はMXレコードの設定、セキュリティを高めるにはSSL証明書(https化)の導入も検討します。SSLはGoogleの検索評価にも関係する重要要素です。DNSレコードの編集やサブドメインの設定も、必要に応じてマイページから行えます。ドメイン取得後は、単なる所有にとどまらず、正確な設定とセキュリティ対策を施すことで、安全かつ効果的に活用できます。
これから記事の外注を検討されている方は、記事制作代行NEOへご相談ください。記事制作代行NEOでは、業界最安水準の文字単価3.5円〜にて制作を行っております。
どの業者よりもリーズナブルかつ高品質な記事制作を行わせていただきます。キーワードの選定・執筆・ワードプレス入稿・リライト・SEO対策まで一括してご依頼いただけます。
まずはお気軽に以下のリンクよりご相談ください!
SEO記事代行制作なら記事制作代行NEOへ!

オウンドメディアの記事制作代行・運用代行であれば記事制作代行NEOへご相談ください。
記事制作代行NEOでは代行相場が文字単価5円以上が一般的なところ、文字単価3.5円より記事制作を請け負っております。
キーワードの選定、記事構成作成、WordPress入稿まで一括してご依頼いただけます。1からオウンドメディアを制作しようとお考えの方も、立ち上げからお任せいただくことが可能です。
まずはお気軽に以下のリンクより無料カウンセリングへお申し込みください。
これから記事の外注を検討されている方は、記事制作代行NEOへご相談ください。記事制作代行NEOでは、業界最安水準の文字単価3.5円〜にて制作を行っております。
どの業者よりもリーズナブルかつ高品質な記事制作を行わせていただきます。キーワードの選定・執筆・ワードプレス入稿・リライト・SEO対策まで一括してご依頼いただけます。
まずはお気軽に以下のリンクよりご相談ください!

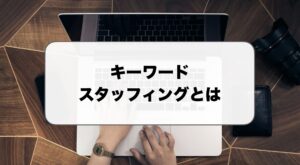

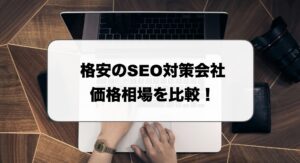
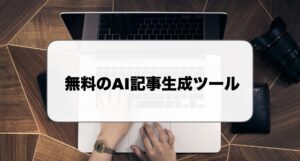
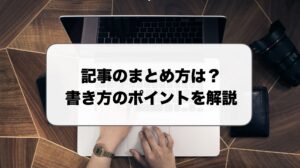

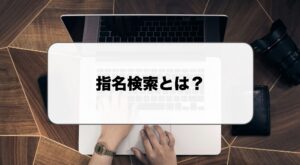
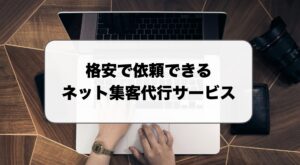
コメント